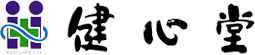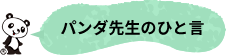例えば「胃痛」の場合・・
まず、胃痛の原因を探ります。
精神的ストレスからなのか、
過飲食よる胃腸の働き低下や
胃粘膜の炎症からくるものなのか、
冷えや血液不足からなのか. .
そしてその原因の根本的なところに働きかける
中国漢方を選び
症状の根っこから
改善していくという方法です。
中医学(中国漢方)の思想
中国の伝統医学である「中医学(中国漢方)」では、
病気になってから治療することよりも
むしろまだ病気になってはいないが
何らかの身体の不調が出ている半分病気の状態
(これを中国漢方では“未病”といいます。)を
治すことがより大切であると説いています。
もちろん、すでに病気になってしまった状態に
対応することもできますが、
症状が出始めた早い段階で
改善し、
大きな病気につながらないようにすることが
一番です。
私たちのお店では、自分では気付かぬままに
健康のバランスを崩している方の改善にお役に立てるよう、
食やその意識の見直しと共に
日本漢方よりも個々の身体の状態をより詳しく診ていく
中国漢方を
取り入れております。
「飲食養生」・「医食同源」は予防医学の基本
二千年前の周王朝の時代には、宮廷に飲食や栄養を
管理する“食医”と呼ばれる医師も置かれていたぐらい、
中国では昔から
「日常の食事に気をつけて病気にならないようにする」
という考え方が重んじられてきました。
その中で、「中国漢方も食べ物も自然から得られるもの」
という見方から、薬(中国漢方)療法と
食事療法を
行います。
〜「薬」と「クスリ」〜
・東洋医学の「薬」→草かんむりに「楽」。
植物などの自然なものを材料とする。
・西洋医学の「クスリ」
→おもに化学物質を材料とする。
「中医学(中国漢方)」において
人体を構成するものとは・・
「気(巡らすエネルギー)」・「血(身体を養うもの)」・「水(体内の有益な水分)」
これら3つは一か所にとどまることなく、
常に体内を巡り続けていることが望ましいのですが、
気の巡りが滞れば「気滞(きたい)」
血の巡りが滞れば「瘀血(おけつ)」
水の巡りが滞れば「痰湿(たんしつ)」
と呼ばれ、病気の大きな原因になってしまいます。
この中でも特に重要となる「血」は、毎日食べている物、
飲んでいる物から作られるため、
食べ物や飲み物の質が
良ければ
きれいな血になり健康を保つことができ、
悪ければドロドロ血液になり病気をおこしてしまう
ということです。
「血(けつ)」のはたらき
①身体のすみずみに酸素と栄養素を運び、
滋養する作用(身体の養生)
②人の精神を養う作用(精神の養生)
③気を生みだし、それを全身に巡らせる作用
(エネルギー産生と生命活動)
④外邪の侵入を防ぎ、身体を守る作用(免疫力)
~「五臓」を養うのも、また「血(けつ)」なり。~
- 「肝」
- 肝臓、筋肉、爪、目、胆のう、自律神経系。
- 「心」
- 心臓、脳、血脈、小腸、循環器系。
- 「脾」
- 脾臓、肌、口、胃腸などの消化器系。
- 「肺」
- 肺、大腸、皮ふ、鼻やのどなどの呼吸器系。
- 「腎」
- 腎臓、骨、髪、耳、泌尿生殖器、ホルモン系。
「瘀血(おけつ)は百病の源」
「瘀」は「淤(水がたまって流れない)」からきた文字。
つまり「瘀血」というのは、血液の流れが滞っている状態を
いい、
具体的には
①血液の循環障害
②血液の汚濁、粘稠
③内出血
④器官の増殖、変性、硬化
⑤各種の腫瘍、がん
などの意味が含まれ、
右下のような症状が現れやすくなります。
主な症状
頭痛・肩こり・関節の痛みやしびれ・動悸・胸の痛み
手足の冷え・月経痛・月経不順・月経血の塊や黒ずみ
便秘・タール状の便・痔・耳鳴り・めまい・疲労倦怠感
ぜんそく・腹水・もの忘れ精神神経症 など
瘀血が続くことによってこのような三大症状
「痛み」・「黒ずみ」・「しこり」が出ている場合は、
なるべく早く改善されることを
おすすめ致します。
病気と老化の予防は、
「血液・血管の健康管理」から
現代の生活習慣病の原因が、飲食の不摂生、過食、
栄養バランスの崩れであることは言うまでもなく、
そこに精神的なストレスが加わってさまざまな症状や
病気の問題が増えていることが考えられます。
いま問題になっている症状や病気は、
ほとんどが血液や血管が原因であるといわれています。
血液や血管の健康を保つためには、毎日の生活に於いて
「排泄、食事、運動、睡眠」のリズムや
バランスを
整えることが一番大事で、
これらが自分の努力では
どうにもならない時、
「食と意識の改善」と共に
「中国漢方の力」を借りて整えていくことができます。
主となる中国漢方
(パンダのマークのイスクラ中成薬・健康食品)
イスクラ冠元顆粒
イスクラ麦味参顆粒
イスクラ婦宝当帰膠
イスクラ杞菊地黄丸
イスクラ頂調顆粒
イスクラ逍遙顆粒
イスクラ勝湿顆粒
イスクラ平喘顆粒
イスクラ衛益顆粒
イスクラ独歩顆粒
星火亀鹿仙
板藍茶&板藍のど飴
パンダマークの中国漢方薬は、国際的な医薬品の製造と
品質管理基準に基づいて製造され、
正規の手続きで
輸入された医薬品です。